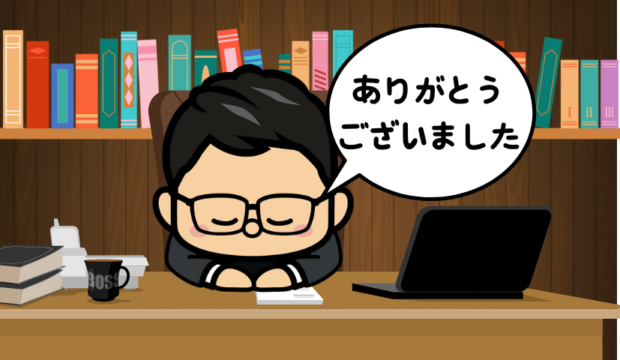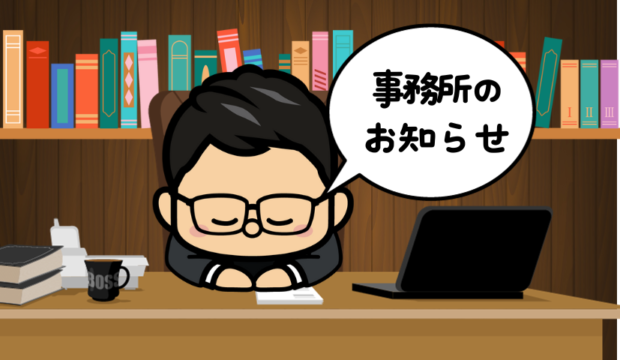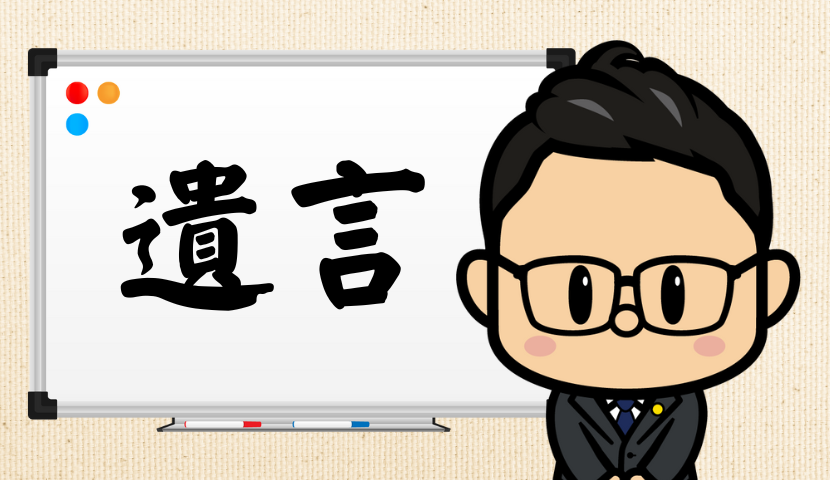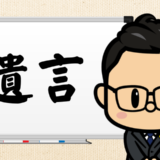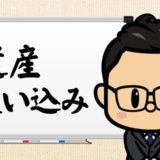こんにちは。永原法律事務所代表弁護士の永原裕也です。
今回は、遺言書の書き方について詳しく解説いたします。
遺言書は、相続トラブルを防ぎ、希望通りの財産分配を実現するために重要な役割を果たします。しかし、書き方に不備があると無効になってしまうこともあります。
この記事では、正しい遺言書の作成方法や注意点を解説し、円満な相続を実現するためのポイントをご紹介します。
なぜ遺言書の書き方が重要なのか?
遺言書がないと相続トラブルが発生する?
遺言書がない場合、相続は民法に基づく法定相続で行われます。しかし、これでは亡くなった方の意思が反映されず、相続人同士の意見が対立する可能性があります。
例えば、財産の大半が不動産の場合、「売却するのか」「誰が住むのか」などの問題が発生し、トラブルになることも少なくありません。
不備があると無効になるケースとは?
遺言書には厳格な形式が定められており、ルールに違反すると無効になります。よくあるミスとして、以下のようなものがあります。
- 日付の記載がない(「令和○年○月○日」など明確に記載する必要がある)
- 署名・押印がない(自筆証書遺言は本人の署名・押印が必須)
- 全文を手書きしていない(自筆証書遺言はパソコンや代筆では無効)
正しい書き方で円満な相続を実現
遺言書を正しく作成することで、家族の負担を減らし、円満な相続を実現できます。次の章では、遺言書の種類とそれぞれの特徴について詳しく解説します。
遺言書の種類と特徴|自分に合った形式を選ぶ
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った形式を選びましょう。
自筆証書遺言:手軽だが形式不備に注意
✅メリット:自分で簡単に作成できる(費用がかからない)
❌デメリット:不備により無効になるリスクが高い。家庭裁判所の検認手続きが必要になる
近年の法改正により、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が始まりました。これにより、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。
公正証書遺言:法的に確実でトラブル回避に有効
✅メリット:公証人が関与するため、無効になるリスクが少ない
❌デメリット:公証役場での手続きが必要(費用がかかる)
確実に遺言を実現したい方には公正証書遺言が最適です。
秘密証書遺言:内容を秘密にしたい場合
✅メリット:遺言の存在は証明されるが、内容は秘密にできる
❌ デメリット:公証人と証人2名にその存在の証明をしてもらうので手間がかかる。不備により無効になるリスクが高い。家庭裁判所での検認手続きが必要になる
遺言書の書き方の主な注意点
1. 形式的な要件
遺言の種類ごとに要件が異なりますが、ここでは「自筆証書遺言」の注意点を中心に紹介します。
・全文を自筆で書く(2020年以降は財産目録のみパソコンでも可)
・日付を明確に書く(例:「令和7年〇月〇日」)
・署名と押印が必要
訂正方法にもルールがある
例えば二重線+訂正印+訂正箇所数の記載など。
2. 内容面の注意点
財産の分け方は、曖昧にせず具体的に記載することが重要です。
❌曖昧な書き方の例
「長男に私の不動産を相続させる」
✅正しい書き方の例
「東京都○○区△△1-2-3の土地(登記簿番号○○)を長男○○に相続させる」
「遺贈」と「相続」の違いを理解する
・相続:法定相続人に財産を渡す場合
・遺贈:それ以外の人や団体に財産を渡す場合(例:法定相続人以外の親族、友人、団体、NPO)
遺留分を考慮しないと争いの原因に
相続人には、最低限保障された遺産の取り分(遺留分)があります。主に、配偶者・子・直系尊属(父母など)に認められており、兄弟姉妹には認められていません。この制度は、遺言者の意思を尊重しつつも、残された家族の生活や権利を保護するために設けられています。
たとえば、遺言で「全財産を長男に相続させる」と記載した場合でも、他の相続人には遺留分を請求する権利があり、それを侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」として金銭の支払いを求めることができます
遺留分を無視した遺言は、残された家族間で不公平感を生み、感情的な対立に発展することがあります。最悪の場合、訴訟にまで発展することもあるため、円満な相続を実現するには、遺留分を十分に考慮した遺言内容にすることが重要です。
実際にどのような配分にするかは、専門家と相談しながら作成するのが望ましいでしょう。
遺言執行者の指定で相続手続きをスムーズに
遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する責任を持つ人のことで、財産の名義変更や分配、必要に応じた手続きなどを行います。
遺言書にこの遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、相続手続きが大幅にスムーズになります。
特に、複数の相続人がいる場合や、相続人以外への遺贈、不動産や預貯金など多様な財産が含まれている場合には、手続きが煩雑になりがちです。
遺言執行者がいると、相続人全員の同意を得ずに手続きが進められる場面も多く、トラブルや遅延を防ぐ効果があります。
✅遺言執行者の役割
・預貯金・不動産の名義変更
・相続財産の管理
・相続人への財産分配
相続人間で感情的な対立がある場合にも、第三者としての執行者が介入することで、中立的な立場から粛々と遺言を実行することができ、相続争いの予防にもつながります。
信頼できる人物や、専門知識を持つ弁護士・司法書士を指定しておくと安心です。
まとめ|遺言書の書き方に迷ったら弁護士に相談を
- 遺言書は正しい書き方で作成しないと無効になる可能性がある
- 財産の分け方は具体的に記載し、遺留分も考慮することが大切
- 公正証書遺言を作成すれば法的に確実な相続が実現できる
- 遺言執行者を指定すると、遺言の実行がスムーズになる
遺言書の書き方に不安がある場合は、法律の専門家に相談するのが安心です。
当事務所では、無料相談を受付中です。お気軽にご相談ください!